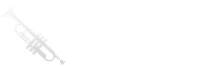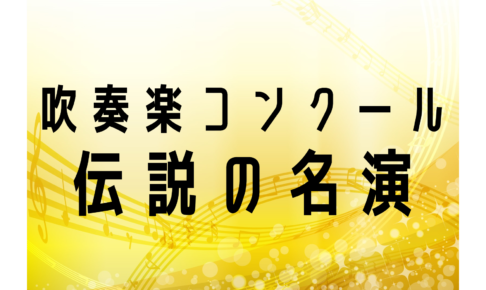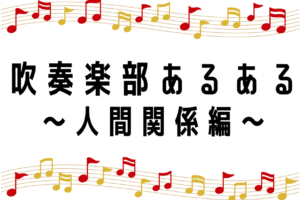吹奏楽コンクール。吹奏楽民が青春をかけて挑む、1年に1度の大イベント。
今回はそんな全日本吹奏楽コンクールの歴史についてご紹介していきます。
吹奏楽コンクールの始まり
全日本吹奏楽コンクール(以下、吹奏楽コンクール)は、参加団体が10000を超える、吹奏楽における国内最大の大会です。
開始から70年近く、長い歴史を持つ大会でもあります。
吹奏楽コンクールの歴史の始まりは、なんと戦前までさかのぼります。
記念すべき第1回の吹奏楽コンクールが開催されたのは1940年。全日本吹奏楽連盟(※)と、朝日新聞社の主催で開かれました。
(※日本の吹奏楽の振興を目的として1939年に設立され、当時は「大日本吹奏樂聯盟」という名称でした。)
1942年に第3回吹奏楽コンクールが行われたあと、太平洋戦争のために一時中断。再開されたのは戦後10年経った1956年でした。
その後は途切れることなく毎年開催され、2019年には第67回めの吹奏楽コンクールを迎えます。
ちなみに、2019年に創立80年を迎えた全日本吹奏楽連盟は、記念誌として「80年史」を刊行。
各主催事業の第1回からの全記録、課題曲などの情報が集約された1冊となっています。
http://www.ajba.or.jp/80th.htm
過去に適用されていた規定・審査方法
70年ちかく続いてきた吹奏楽コンクールですが、その長い歴史の間に、規定・審査方法などを必要に応じて変化させてきました。
過去に適用されていたものの一部をご紹介します。
三出制度
本選である全国大会への代表出場に関して、数年前まで適用されており、名門校の証でもあったのが「三出制度」です。
三出制度とは、3年間連続して全国大会に出場した団体は、その翌年には吹奏楽コンクール(下位大会も含め)に参加することができない、というものでした。
1994年から1998年は、3年間連続して全国大会で「金賞をとった」団体(いわゆる三金)でしたが、1999年からは「出場」が条件となりました。
毎年のように強豪校が代表出場の枠を独占していた状況と、「少しでも多くの団体に全国大会の舞台を経験してほしい」という主催者サイドの思いがあって、最近まで施行されていた制度です。
このルールによって、全国大会への出場を経験できた学校や団体もあったかと思いますが、対象の学校にとっては、毎年メンバーが違うのにも関わらず4年に1度は吹奏楽コンクールの予選にすら参加できない年があり、賛否両論の制度でもありました。
2013年にはこの制度は廃止。実力勝負の世界となりました。
過去の審査方法
全国大会の審査方法も、最近になって大きな変更がなされました(本選である全国大会の審査方法であり、支部大会以前の予選の審査方法はこの限りではありません)。
現在の審査方法は、9人の審査員が課題曲と自由曲を総合して、A・B・Cの三段階で評価し、過半数がAなら金賞、過半数がCなら銅賞、それ以外は銀賞となる、というものです。
しかし、2013年以前には、もっと細かい審査がされていました。
まず、課題曲と自由曲それぞれに、「技術面」と「表現面」という2つの側面からの評価がされていました。
評価はA・B・C・D・Eの五段階で、それをさらに得点化し、合計点の高い順に金・銀・銅が決まりました。
さらには、極端な点数に引っ張られないよう、1番高い点数をつけた審査員と1番低い点数をつけた審査員の評価がカット(いわゆる「上下カット)されていました。
現在の審査方法では、審査員のつけられるA・B・Cの数は決められているものの、それまでの審査方法に比べると、多少ざっくりした採点になった感じがしますね。
吹奏楽コンクールの会場の変遷
「吹奏楽の聖地」、普門館
2012年から現在まで、吹奏楽コンクールの中学・高校の部の全国大会会場となっているのは名古屋国際会議場センチュリーホールです。
しかし、吹奏楽コンクールの歴史を語るうえで欠かすことができないのが、35年に渡って中学・高校の部の全国大会会場として使われた普門館の存在です。
普門館とは東京都杉並区にあった、宗教法人「立正佼成会」の所有していたホールで、1972年に初めて会場となり、その後、1977年から2011年まで(2005年を除く)使用されました。
コンクールを目指す吹奏楽部の学生たちにとっては憧れの場所であり、「吹奏楽の聖地」とも呼ばれていました。また、たびたびテレビで取り上げられることで「吹奏楽の甲子園」として一般の間でも有名になりました。
耐震強度不足が判明し2012年に使用が停止され、立地の問題から立替もかなわず、惜しまれながら2018年冬に解体となりました。
解体前に行われた1週間の一般公開には1万2千人が訪れ、憧れのステージ・思い出の場所で最後の時間を楽しみました。
毎年会場の変わる大学・職場・一般の部
一方、大学と職場・一般の部の全国大会では決まった会場はなく、各支部の持ち回りで全国様々な会場で開催されています。
2019年の全国大会は、東北支部のリンクステーションホール青森で開催されることが決まっています。
吹奏楽コンクールの課題曲の移り変わり
ご存知の通り、吹奏楽コンクールでは課題曲と自由曲、2曲の演奏で審査されます。
このうち課題曲は、吹奏楽連盟の指定した数曲の楽曲中から選んで演奏することになっています。この課題曲の決められ方や規定についても、60年以上の歴史の中で様々に移り変わってきました。
順を追って見ていきましょう。
第1回~第3回(1940~1942年)
戦前に行われた3回の吹奏楽コンクールでは、愛国心を鼓舞するような課題曲が選ばれていました。
大行進曲『大日本』、行進曲『皇軍の精華』、行進曲『航空日本』というように。
この最初の3回に関しては時代柄、吹奏楽以外にも、喇叭隊(らっぱたい)、鼓笛隊(こてきたい)、喇叭鼓隊(らっぱこたい)などの部門がありました。
第4回~第21回(1956年~1973年)
中学、高校、職場、大学・一般、あるいは中学の部とそれ以外など、部門の分け方は微妙に変化しましたが、それぞれに各1曲、課題曲が指定されていた時代です。
初期には外国人作曲家の曲も多く、たとえば第4回と第5回では、スーザ(John Philip Sousa)の『エル・キャピタン(El Capitan)』『マンハッタン・ビーチ(Manhattan Beach)』がそれぞれ選ばれていました。
他にも、第7回に選ばれた團伊玖磨の『祝典行進曲』や、第18回のリード(Alfred Reed)『音楽祭のプレリュード(A Festival Prelude)』など、現在でも演奏され続けている有名曲も課題曲になっていました。
第11回までは全ての課題曲が行進曲でした。
第22回~第40回(1974年~1992年)
第22回からは、部門に関係なく好きな課題曲を選べるようになりました(第23回と第25回は例外)。
課題曲の曲数は第22回のみ2曲、それ以降はほとんど4曲で、27回と35回が5曲でした。
楽曲は、連盟が委嘱した作品に加えて、公募で受賞した作品、39回からは朝日作曲賞の受賞作品が課題曲に選ばれるようになりました。
第23回からは、課題曲の参考音源(プロによる演奏見本)の販売が開始されています。演奏は、東京佼成ウインドオーケストラとOsaka Shion Wind Orchestra(旧・大阪市音楽団)が行っています。
第25回には、今でも大人気の楽曲である、東海林修作曲の『ディスコ・キッド』が課題曲に選ばれました。
『ディスコ・キッド』は、2009年5月24日放送のテレビ朝日「題名のない音楽界」にて、視聴者が選んだ吹奏楽人気曲ベスト10の1位に輝いた曲でもあります。
第41回~第55回(1993年~2007年)
第41回大会からは、課題曲の全てが、西暦で奇数年はマーチの楽曲、偶数年はマーチ以外の楽曲、と交互に選ばれるようになりました。
曲数は50回までは4曲(44回のみ5曲)、51回からは5曲になり、課題曲Ⅴは大学・職場・一般の部のみが選択可能でした。
この15年間の課題曲からも、真島俊夫『五月の風』、福島弘和『稲穂の波』、高橋伸哉『行進曲「K点を越えて」』など、今でも愛され演奏され続けている名曲が数多く生まれました。
第56回~現在まで(2008年~)
マーチ楽曲とそれ以外の楽曲が交互に課題曲になるという規定が変わって、56回からは、毎年両方の楽曲が課題曲に含まれるようになりました。
課題曲Ⅰ~Ⅳは、マーチの楽曲が2曲、それ以外の楽曲が2曲。
朝日作曲賞の受賞曲と入選曲に、年度によっては連盟委嘱作品が加わります(65回以降、1曲は委嘱曲が入ることになりました)。
課題曲Ⅴには、「全日本吹奏楽連盟作曲コンクール」で第1位になった作品が選ばれます(マーチも可能)。「全日本吹奏楽連盟作曲コンクール」は、連盟発足70周年を記念して2009年から始まりました。
課題曲Ⅴは、高校、大学、職場・一般の部のみ選択可能です(第56回までは、高校の部も選択不可でした)。
2019年の課題曲は、Ⅰ~Ⅳのうち、委嘱作品を含む3曲がマーチとなっています。
数々の名曲が生まれてきた吹奏楽コンクール。こちらの記事もぜひチェックしてみてください。
吹奏楽コンクールの社会認知度と入場券
テレビやラジオなどでは定期的に吹奏楽コンクールが取り上げられています。特に『笑ってコラえて 吹奏楽の旅』は大きく話題になりました。強豪校の練習風景や、演奏も吹奏楽コンクールの認知度アップに大きく貢献しました。
最近では吹奏楽をテーマにしたアニメシリーズ『響け!ユーフォニアム』が人気となったり、吹奏楽が話題になるケースが増えてきているのは嬉しい限りです。
吹奏楽コンクール全国大会の、入場希望者も会場のキャパシティを大幅に上回るほどになり、1992年には当日券の販売が廃止され事前受付のみになるなど入場券は次第に入手困難なプラチナチケットとなっていきました。
2018年現在、一般席は全て指定席で、販売方法はインターネットでの事前申込となっています(中学・高校の部は抽選、大学・職場・一般の部は先着)。
弊ブログでもこちらの「吹奏楽コンクール全国大会出場・金賞回数ランキング」という記事が、年間最も見ていただいている記事で、年間最も見られている記事ですが、吹奏楽コンクールや、出場校・強豪校への注目度の高さを実感しています。
ということで、吹奏楽コンクールの歴史を振り返ってきました。
長い歴史とともに、数えきれない様々なドラマが生まれてきただろうこと思うと、とても感慨深いですね。
これからも、吹奏楽コンクールで生まれるたくさんのドラマと名演に注目していきましょう!