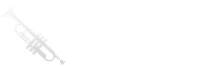定期演奏会の1曲目は、お客さんの心を一気に惹きつける、華やかな曲がいいですよね。
今回の記事は、オープニング曲にピッタリ!演奏会の1曲目にふさわしい吹奏楽曲10選。
筆者が悩みに悩んで厳選した10曲をご紹介します。
『フィエスタ!』
『フィエスタ!(Fiesta!)』は、イギリスの作曲家フィリップ・スパーク(Philip Sparke)がアメリカ陸軍フィールド・バンドに委嘱されて作った楽曲です。
演奏時間は7分前後。
吹奏楽を語るうえで欠かすことのできない、数々の名曲を生み出しているスパーク。
『フィエスタ!』は演奏会の曲目としてはもちろん、吹奏楽コンクールの自由曲としても頻繁に演奏されています。
ぐんぐん曲が進む疾走感、メロディアスな曲調がオープニングに最適で、グレードも4と取り組みやすさもメリットです。
鮮やかなラストスパートで、お客さんの心を一気に掴みましょう!
『オリエント急行』
同じくフィリップ・スパーク作曲の『オリエント急行(Orient Express)』。
演奏時間は8分前後。
250曲を超える吹奏楽曲を作っているスパークですが、そのたくさんの作品の中でも『オリエント急行』の知名度は群を抜いているのではないでしょうか。
ワクワクと心が躍る賑やかな機関車の旅を、吹奏楽で見事に表現した楽曲ですね。
機関車の汽笛、蒸気を出してゆっくりと発車する様子を表現するために、打楽器の笛や小物たちが大活躍します。
曲の雰囲気を目と耳から存分に味わうことができ、客席で見ているお客さんも楽しめるはず。
「今から演奏会という吹奏楽の旅が始まりますよ」というメッセージを込めることもできて、オープニング曲にもってこいの楽曲だと思います。
『アルセナール』
『アルセナール(Arsenal)』は、ベルギーの作曲家ヤン・ヴァンデルロースト(Jan Frans Joseph Van der Roost)の代表曲であるコンサートマーチです。
演奏時間は3分半前後。
当ブログの記事「テンションが上がる⤴吹奏楽のマーチ名曲ランキングベスト10」でも1位に選んだこの曲は、もちろんオープニング曲にもうってつけ!
コンサートマーチらしい華やかさと気高さ、万人の胸を打つ感動的なメロディーを併せ持っている名曲です。
終盤のGrandioso(「壮大に」の意)からは落ち着いたテンポで堂々と聴かせるも良し、オープニングらしくテンポを落とさず爽やかに吹き抜くも良し。
演奏時間も短く、1時間程度のコンサートにも取り入れやすい楽曲です。
『フラッシング・ウインズ』
同じく、ヤン・ヴァンデルロースト作曲の『フラッシング・ウインズ(Flashing Winds)』。
演奏時間は4分~4分半です。
『フラッシング・ウインズ』は『アルセナール』よりも先に作られた、ヴァンデルロースト作品の中でも初期のものですね。
ティンパニのソロに続くファンファーレの厳かな雰囲気から、晴れやかにメインテーマに移行するのが気持ち良い!
青少年バンドの委嘱により作曲されたという経緯、そして「フラッシング(きらめく)・ウインズ(風と管楽器をかけていると思われます)」のタイトルも示す通り、生き生きとエネルギッシュな楽曲です。
とにかくかっこいい曲で、オープニングを盛り上げるのにぴったり。
変拍子が多いのが少々大変ですが、ぜひチャレンジしてみてほしい1曲です。
『五月の風』
日本の誇る吹奏楽界の傑氏、真島俊夫(Toshio Mashima)作曲の『五月の風』。
演奏時間は3分半程度。
第45回(1997年) 全日本吹奏楽コンクールの課題曲Ⅲに選ばれ、全国大会では半数以上の団体が課題曲にこの曲を選択したそうです。
その後も長く愛され、多くの団体が演奏会の曲目に取り入れています。
当ブログでもたびたび取り上げてきた曲で、「吹奏楽コンクール課題曲の名曲ランキングベスト10」では4位、「テンションが上がる⤴吹奏楽のマーチ名曲ランキング」では5位に選んでいます。
タイトル通りの爽やかな曲調と快活なテンポ感はまさにオープニング向け。
弾むようなメロディーの中にも低音のおおらかさがあり、木管高音とグロッケンのキラキラが華を添えます。
3分半という演奏時間は短時間の演奏会でもプログラムに取り入れやすく、とってもおすすめです!
『キャンディード序曲』
『キャンディード序曲(Overture to Candide)』は、舞台『キャンディード』で演奏される序曲。
演奏時間は4~5分。
作曲したレナード・バーンスタイン(Leonard Bernstein)は、アメリカの作曲家・指揮者・ピアニストで、あの有名なミュージカル『ウエスト・サイド物語(West Side Story)』の音楽も作曲しています。
ちなみに、舞台としての『キャンディード』の原作は、フランスの思想家ヴォルテールの『カンディード或は楽天主義説』という小説です。
吹奏楽版の『キャンディード序曲』は、ミュージカルで演奏されているオーケストラ編成の曲をアメリカの作曲家クレア・グラントマン(Clare Grundman)が編曲したもの。
スピーディなテンポ、躍動的で目まぐるしく変化するメロディーが特徴の、忙しくもユーモラスで楽しい1曲です。
天真爛漫な主人公キャンディードの波乱万丈なストーリー、その幕開けを飾るこの序曲は、オープニング曲の候補としても外せない1曲。
唐突に始まるファンファーレで、聴衆の心をがっしりと捉えることができるはずです。
『アルヴァマー序曲』
吹奏楽作品として、不動の人気と知名度を誇る『アルヴァマー序曲(Alvamar Overture)』。
演奏時間は7分半強。
青春の思い出がよみがえる、大好きな曲だという吹奏楽経験者も多いのではないでしょうか?
中高生ならば、演奏会のメインの1曲として扱うこともあると思います。
作曲者は、アメリカの作曲家・指揮者であるジェイムズ・チャールズ・バーンズ(James Charles Barnes)。
他に、『祈りとトッカータ(Invocation and Toccata)』『パガニーニの主題による幻想変奏曲(Fantasy Variations on a Theme by Nicolo Paganini)』などの作品があります。
親しみやすいメロディーと心地よいテンポ感は演奏会のオープニングにも向いています。
演奏時間は7分半強としていますが、6分半強の快速スピードで駆け抜けるプロの演奏も。
『The Seventh Night of July(たなばた)』
疾走感のあるメインテーマや中間部のロマンティックなメロディー、星空や流れ星を思わせるキラキラしたイメージなど、魅力たっぷりの「The Seventh Night of July(たなばた)」。
演奏時間は8分半前後。
坂井格(Itaru Sakai)作曲、吹奏楽界の超有名曲であり超人気曲ですね。
当時自分が好きだった吹奏楽曲や歌謡曲など、様々な作品から引用したフレーズをたくさん盛り込んだという作曲者の坂井格氏ですが、これを書きあげた時はまだ高校生だったというのですから、本当に驚きですよね。
取り組みやすい難易度で、『アルヴァマー序曲』と同じく定期演奏会のメイン楽曲に据えることも多いであろう、起伏に富んだ聴きごたえのある曲です。
こちらの演奏時間もやや長めですが、大学生以上の団体や強豪校なら演奏会のオープニングに使うのにもおすすめの1曲。
吹奏楽に関わりのある人間なら馴染みのある曲なので、どれだけ聴かせられる演奏ができるか腕の見せ所ですね。
『ヴィヴァ・ムジカ!』
『ヴィヴァ・ムジカ!(Viva Musica)』はアルフレッド・リード(Alfred Reed)の作品。
演奏時間は4分半前後。
シカゴのヴァンダークック音楽大学の委嘱作品として作られたこの曲には、リードによって音楽の楽しさ、素晴らしさのイメージが詰め込まれています。
副題には「A concert overture for winds(吹奏楽のための演奏会用序曲)」 とあり、オープニング曲を意識して書かれています。
ゆったりとした中間部はなく、曲はスタートから快活にどんどん展開していきます。
2/4拍子、3/4拍子、7/8拍子、8/8拍子と、頻繁に変化する拍子を合わせるのがこの曲の1番の難しさでしょうか。
タイトルの意味は「音楽万歳」。
吹奏楽の楽しさを味わいながら演奏できれば、コンサートの素敵なスタートが切れそうです。
『吹奏楽の為の序曲』
最後に紹介するのは、『吹奏楽の為の序曲』。
演奏時間は5分半強。
坂田雅弘(Masahiro Sakata)作曲、平成12年度(2000年) 第48回全日本吹奏楽コンクールの課題曲Ⅳでした。
名曲揃いだったこの年の課題曲の中でも、ファンが多かったこの曲。
難易度が高かったためにあきらめざるを得なかった学校・団体もあるのではないでしょうか。
木管の細かな連符のクレッシェンドから始まる導入部は、まさに幕開け!というイメージ。映画やゲームのオープニングのような雰囲気もあります。
躍動的な主題には一聴変拍子かのような動きがあり、ここを揃えるのが要になってきます。
そして、曲の半分近くを占める中間部の旋律がとても素敵!
個人的に、数ある吹奏楽曲の中でもベスト5に入るほど好きなメロディーです。
木管からトランペットのソロへの、自然な主旋律の受け渡し。
いくらかさっぱりとしたフィナーレも、次の曲へとつなぐオープニング曲としては効果的ではないでしょうか?
あまり知名度が高くないようですが、とてもいい曲なのでぜひ1度音源を聴いてみてほしいです。
演奏会の1曲目を飾るのにふさわしい吹奏楽曲を10曲ピックアップしてご紹介しました。
オープニング曲の選曲に迷ったときは、参考にしてみてくださいね!