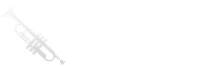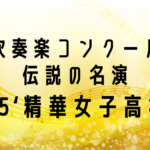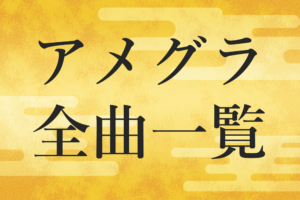今回は、20世紀吹奏楽の記念碑的作品、とも言われる名曲で、その難易度でも知られる『フェスティヴァル・ヴァリエーション(Festival Variations)』をご紹介します。
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』はどんな曲?
作曲者はクロード・トーマス・スミス(Claude Thomas Smith)。
このブログでも『華麗なる舞曲』・『ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲』をご紹介しておりそこでも触れている通り、吹奏楽のヒットメーカーであり、屈指の「難曲メーカー」としても知られています。
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』はこれらの曲の中でも、最も有名と言っても過言ではない1曲で、吹奏楽民の間では『フェスバリ』と略されて呼ばれていたりもします。
この曲は、アメリカ空軍ワシントンバンドと、当時の隊長を務めていたアーナルド・D・ゲイブリエル大佐の委嘱により作曲されました。
ゲイブリエル大佐は『フェスティヴァル・ヴァリエーション』について「高度な演奏技術と現代的な奏法、ロマンティシズム溢れるサウンドの全てが凝縮されたこの作品は、間違いなく今世紀の記念碑的作品となるだろう」という称賛コメントをフルスコアに記しています。
ホルンが大活躍!『フェスティヴァル・ヴァリエーション』の難しさのポイントとは!?
C.T. スミスは自身がホルン奏者であることから、彼の楽曲においてホルンパートが特に難しいことはよく知られていますが、『フェスティヴァル・ヴァリエーション』はその中でもズバ抜けてその傾向が強い曲です。
この曲を委嘱したアメリカ空軍ワシントンバンドの、当時の首席ホルン奏者が、大学時代のC.T. スミスのライバルであったことから、わざと難しく書いたという有名なエピソードが残っているそうです。
冒頭、いきなりホルンパートの力強いテュッティで始まります。ホルン奏者が一人も音を外すことなく決められるかどうか、最初の最初にこの曲の勝負が訪れます。
そしてこのフレーズはこの後何度も登場します(笑)
この曲のもう一つのキーパートは、パーカッション、中でもスネアドラムが非常に重要な役割を担います。冒頭からスネアドラムがテンポを刻むキーパートであり、この曲のノリを左右します。
ここからメロディーが段々と変奏していきます。
前半部の終わりにも、ホルンパートに難所、ベルトーンが訪れ、息をつく暇がありません。
そして中間部もまた、ホルンスタート。ホルンのゆったりとした長尺のソロで幕開けします。
その後は変奏ソロのリレー。チューバー⇒ユーフォニアム⇒バスクラリネット⇒ファゴットと続きます。
その後は、ホルンソロのメロディーが、木管楽器を中心としたテュッティにより演奏されます。
オーボエ&ファゴットのソリなどを経て、再度バンド全体のテュッティに。
ホルンパートのハイトーン裏メロ、トランペット、トロンボーンを中心とした金管楽器のド派手な伴奏は、この曲のクライマックスの一つです。
コントラバスクラリネットのソロを経て、曲は後半部へ。
テンポが一気に上がり、派手なファンファーレが奏でられます。ここでも主役はホルン、テュッティでド派手なハイトーン連符をホールに響かせます。
メロディーは変奏しながら、金管楽器によるフーガへ突入。聴いている分には、金管楽器に注目がいきがちですが、この裏の木管楽器の連符はどんどん細かくなっていき、かなりの難易度です。
その後、前半部のテーマに戻り、フィナーレへ向かいます。
フィナーレ部分ではホルンの冒頭のフレーズが繰り返され、終盤で疲れ切ったトランペットパートにも、ここへきて難易度の高いハイトーンの連符が課されます(笑)
バンド全員が連符で駆け上がり、盛大なラストを迎えます。
アメリカ空軍バンドによる超絶演奏~YOUTUBEで聴ける音源~
こちらも同じアメリカ空軍バンド×ガブリエル大佐。テンポは落ちますが、こちらも素晴らしい演奏です。
日本のバンドですと、東京佼成の演奏が、安定感あってステキな演奏です。
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』を語るにあたって、アマチュアで外せないのが、精華女子高校ですね。
2013年の吹奏楽コンクール全国大会。冒頭の迫力凄いです。女子校の演奏とは到底思えません(笑)
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』の音源・CDはどこで手に入る?
日本においても屈指の人気曲だけあって、シエナ、東京佼成、大阪市音の3大吹奏楽団が、全てCDを発売しています。個人的には、佐渡×シエナが好きです。
また、デジタルデータで1曲購入も可能です。(東京佼成の音源はこちらからご確認ください)
>>amazonで『フェスティヴァル・ヴァリエーション』音源を探す
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』の楽譜はどこで手に入る?
ブレーンなど各出版社のほか、楽天市場でも購入することができます。
さて、そんなわけで、『フェスティヴァル・ヴァリエーション』を紹介してきました。吹奏楽人生で、一度は演奏してみたい曲の一つ、是非挑戦してみてくださいね(・∀・)!