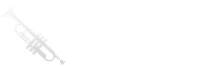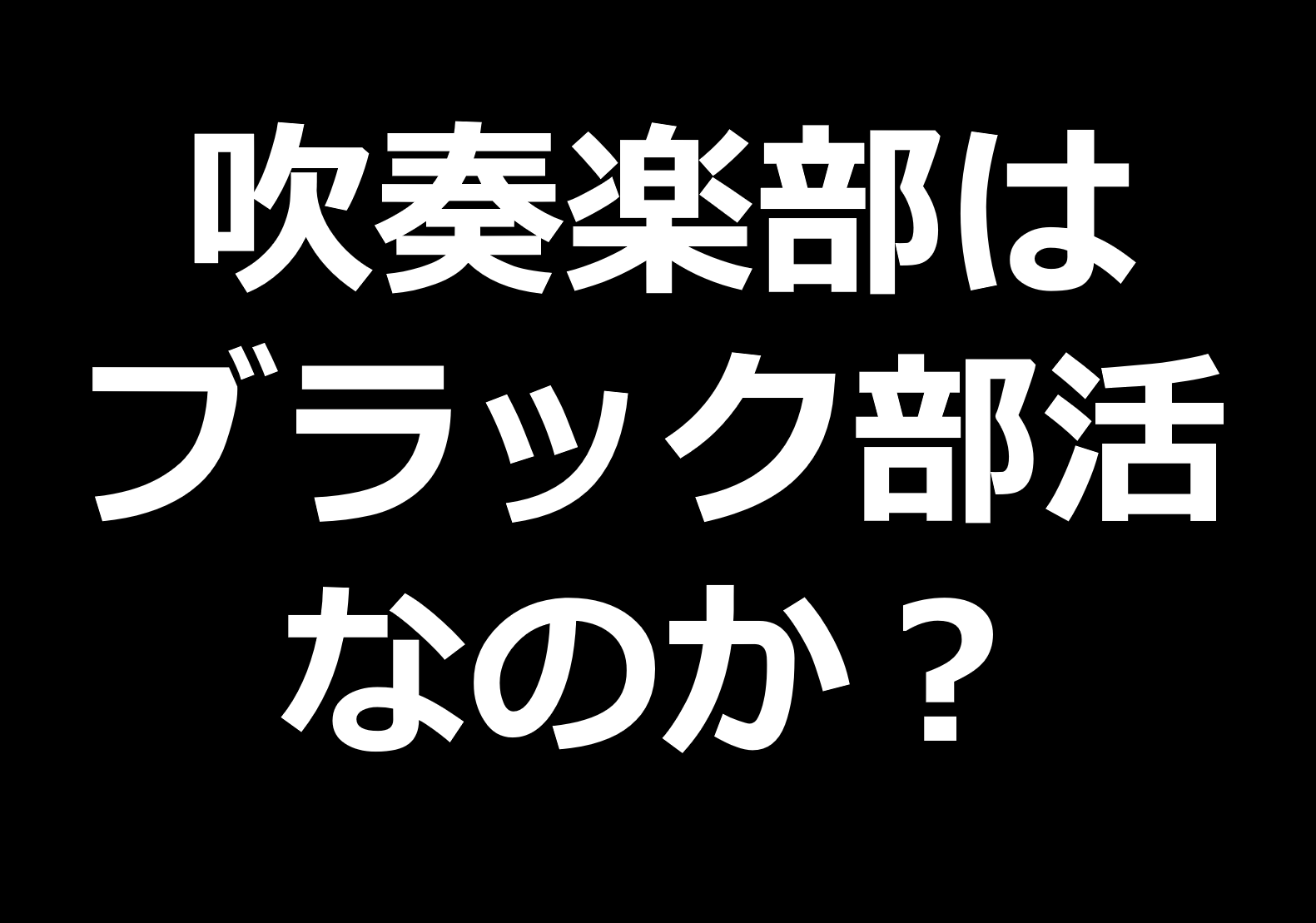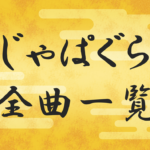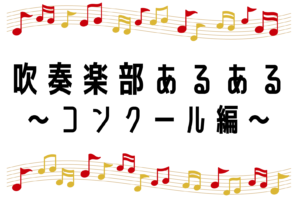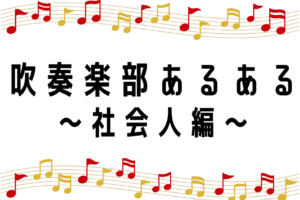「吹奏楽部はブラック部活」そんな風潮が近年急に湧き始めていますね。。
某テレビ番組がきっかけと言われていますが、最近先日私が目にしたネット記事では、たった1人の経験を取り上げて吹奏楽部をブラック呼ばわりしているもので、「吹奏楽部=ブラック部活という結論ありき」のものが多いと感じています。
吹奏楽部での経験が、今の人生を豊かにしてくれていると感じる私としては、この風潮はとても悲しいですし、同じ気持ちの吹奏楽民は多いのではないでしょうか。
ということで、今回当ブログでもこの問題について、指摘されているブラック要素に触れながら、想いを語ってみたいと思います。
運動部のようなトレーニングが常態化している!?
「吹奏楽部はブラック」の風潮の中で、まず言われているのが腹筋やランニング等の運動部のようなトレーニングが状態化しているというもの。
確かに、そういう部活があるのも事実でしょう。ただ、全ての学校というわけではないですし、私の周りの吹奏楽民でも経験者の方が少ないです。「吹奏楽はブラック」な論調の記事の中には、ほとんどの吹奏楽部で、みたいな表現をしているものもありますが、事実誤認だと思います。
そもそも個人的にも、運動能力と吹奏楽の実力は正直大きく関係ないと思っていますし、運動部のようなトレーニングをする吹奏楽部は最近ではさらに少数派になっていると思います。
もちろん体力的にはあったほうがよいに越したことはないでしょうが、プロ奏者ってムキムキな人ばっかりでしたっけ!?笑
私自身の経験では、中学校の吹奏楽部は、ランニングや水泳が課される部活でしたが、高校の吹奏楽部は一切ありませんでした。
ちなみに前者はコンクールB部門予選落ちの吹奏楽部、後者はA部門で支部大会まで進む吹奏楽部でした(笑)
肺活量も多いに越したことはないですが、息の使い方、腹式呼吸のマスターの方がよっぽど重要。そういうことを理解せずに、筋トレ、ランニングなばかりを強要するような指導者は、今後絶滅していくと思います。
暴言が飛び交う!ブラック指導者が存在!?
ここは正直とても難しい話。
一つには時代背景もあるんじゃないかなと思っています。
スポ根、指導者絶対みたいなのは、むしろ吹奏部だけでなく、全てのジャンルの部活に共通することかなと。そして、最近では同様に全てのジャンルでそういうものは見直されてきていると思います。
吹奏楽部の強豪校におけるそういったシーンはインパクトがありますから、TV番組で取り上げられがちで、目だってしまうというのもあると思います。
前提として、人格を否定するような言葉や、やり方は論外だと思っていますし、そういいうものは糾弾されるべきです。
ただ、企業でもそうであるように、今の若い人達は特に、厳しいだけではついていきませんから、厳しさの裏の愛情をちゃんと感じているでしょうし、厳しいシーン以外にフォローしている部分も必ずあるはずです。
私自身、高校時代は支部大会までいく学校でしたので、指揮者の先生もトレーナーもそこそこ厳しかったですけど、常に生徒として愛情は感じていました。だからこそ、今でも先生たちとは交流があります。
支部大会で結果がダメだった時に、いつも厳しいトレーナーの先生が「みんなのせいじゃない」といって涙を流されたときは、男子校吹奏楽部員たち号泣、こんなのも含めて青春だったな、とは思います(笑)
壮絶な競争社会
レギュラーやソリストを決める時の、敗者の号泣シーンなど壮絶な場面も、TV番組では取り上げられがちで、これもやり玉にあがるシーンなのかなとも思っています。
しかしながら、努力に努力を重ねて、ポジションを勝ち取ること、また失敗や挫折から、学ぶことは本当にたくさんあります。
社会に出たら、誰しもが失敗と挫折の繰り返し。そんな経験を学生時代からできるというのは、恵まれていることなのではないかなとも感じます。
また近年ではゆとり教育の揺り戻しで、あえて競争環境をつくって優秀な学生を育てる私立の学校の人気が上がっているとも聴きます。
過密な練習日程
これも中々難しい問題で、特に主観が強くなってしまう点、お許しください。
高校時代の私は、支部大会に進む吹奏楽部だったと書きましたが、私の学校は3年生の大半が受験のため引退して1、2年生でコンクールに臨む学校でしたので、その影響もあり、練習時間は確かに今覚えば長かったです。
朝練は当然ありましたし、夏休みは毎日練習。休みは年末年始以外ありませんでした。笑
ただし、当時は部活楽しくてしょうがなかったですし、上達したくてヒマさえあれば楽器を吹きたくて仕方なかったので、それがつらい、とは感じなかったです。
それこそが、ブラック洗脳である、と言われればそれまでですがw
理想で言えば、効率的に上達できるのが一番。大人や指導者達は努力してここを考えていきたいですよね!
ただ、どんなことであれ結果を出すには人並み以上の努力は必要ですし、なにより「四六時中楽器を吹いていたい」「とにかく吹奏楽部の活動が楽しい」そんな子供達もいるってことは伝えておきたいです。笑
要は大事なのは、どちらにも極端にならないということかな。
最後に・・・
問題のある吹奏楽部が一部存在するのも、おそらく事実なのでしょうが、昔に比べて、理不尽やブラックを許さなくなってきているのが時代の風潮で、もはや生徒や親御さんたちも黙ってはいません。そういう吹奏楽部や指導者は自然となくなっていくはずです。
だからこそ世「吹奏楽部はブラックだ」なんて一義的に騒いで子供達のやる気をそぐのではなく、「子供たちが一生懸命頑張って成長する」「子供達が思う存分、音楽をや楽器を楽しむ」環境である、日本全国の吹奏楽部がより発展していくことを切に願いますし、当ブログも微力ながらその力になっていきたいと思っています!