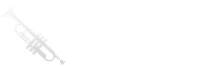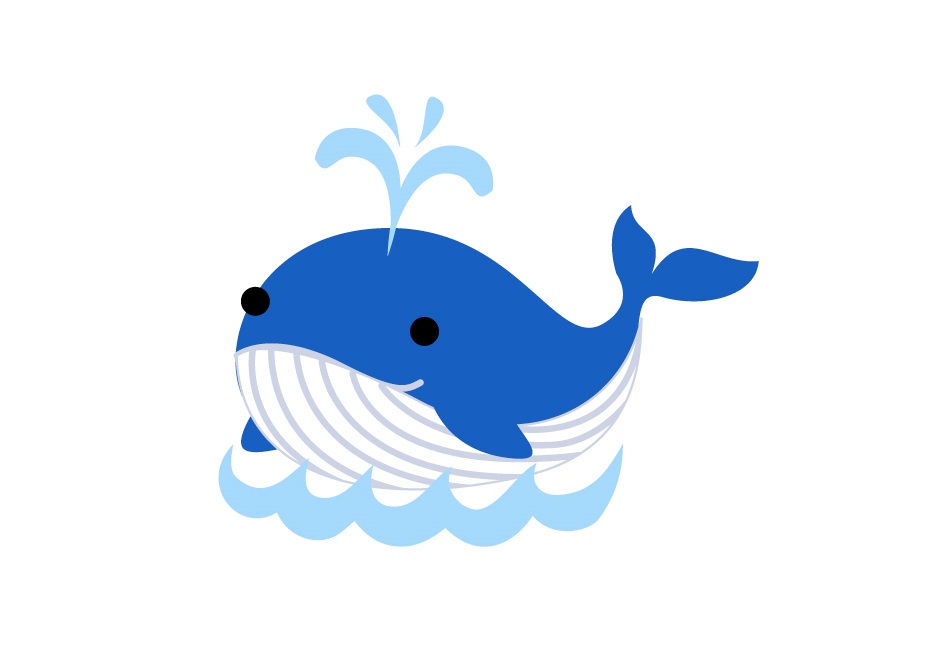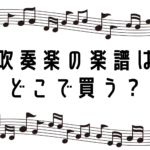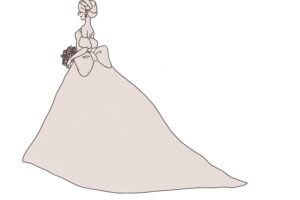英題の『Song of Sailor and Sea』を直訳すると「船乗りと海の歌」。なぜだか日本では『海の男達の歌(Song of Sailor and Sea)』の曲名で知られる吹奏楽の人気曲を紹介します。
『海の男達の歌』はどんな曲?
作曲者はロバート・W・スミス(Robert W. Smith)。
吹奏楽民の間では、『フェスティバルヴァリエーション』や『華麗なる舞曲』で知られるクロード・トーマス・スミス(Claude Thomas Smith)。と区別して「Rスミス」・「RWスミス」なんて呼ばれていたります。
文字通り、「海の男(船乗り)」がテーマになった1曲。そこまで長い曲ではないので、聴いている分には気づかないのですが、実は3楽章構成の曲です。冒頭はオーシャンドラムによる波の音で始まり、夜明け、船出をイメージさせる、ベルの音やトランペットとホルンのメロディで始まります。
3楽章構成の『海の男達の歌』
1楽章:「シーシャンティ(Sea Chanty) 」
「シーシャンティ(Sea Chanty) 」は船乗りの歌を意味します。大海原へ突き進んでいく船乗りたちの豪放磊落な雰囲気がスピーディなメロディで表現されます。クラリネットのメロディで始まり、フルートの裏メロ、やがて金管楽器がそれに加わります。
冒頭のトランペットの「ハイB♭の決め」は前半の聴きどころの一つでこれが決まると、奏者も観客もテンションが一気に上がります(笑)個人的にはチューバが木管楽器と同じパッセージを一緒に吹くテュッティの部分もかっこよくて大好きです。
2楽章:「ホエールソング(Whale Song)」
「ホエールソング(Whale Song)」は「クジラの歌」ですね。 激しい海原が一転、夜の海の静かな雰囲気に変わります。静寂の中、ユーフォニアムがメロディを奏で、フレーズはオーボエへと受け渡されます。
ピアノ伴奏をバックに奏でられるオーボエソロは、この曲の聴きどころの一つ。ホールいっぱいに広がるせつないメロディは観客を虜にします。日本では吹奏楽の超名門、柏高校が吹奏楽コンクール全国大会でこのソロをアルトサックスで演奏したことから、オーボエではなくアルトサックスで演奏されることも多いですが、アルトサックスVerもまたたまらなくステキです。
3楽章:「レーシング・ザ・ヤンキークリッパー(Racing the Yankee Clipper) 」
ヤンキークリッパーはアメリカ高速帆船のことのようです。2楽章の静寂が終わると、一息おいて始まるホルンパートのソリ(Soli)。盛大で華々しい出航のファンファーレが奏でられます。
その後はパーカッションに誘われて、バンド全体でファンファーレが繰り返された後、1楽章同様のスピーディーな展開に戻ります。この楽章はとにかく「スピーディー&パワフル」。そして主役はなんといってもトロンボーン。私がこの曲を演奏した時は、トロンボーンパートのパワフルなSoliを聴きながら「シャチが並んで、高速で海で競争をするイメージ」を勝手に頭に描いていました(笑)
トロンボーンと対抗するようにホルンパートも豪快なSoliで合流。その後、1楽章冒頭のパッセージに戻った後に、再度テンポを上げてフィナーレへ。しかしながら特に金管楽器は最後まで気を抜けません。体力を削られるパッセージが続き、盛大に終曲を迎えます。
『海の男達の歌』といえば柏高校の演奏~YOUTUBEで聴ける音源~
個人的な主観にはなりますが、この曲が日本で流行するきっかけになったのは、1998年吹奏楽の名門、柏高校吹奏楽部の演奏ではないかと思っています。
冒頭のカモメの鳴き声で、観客のアテンションを集め、高校生らしい溌剌としたサウンド、そして高校生離れした中間部の切なすぎるアルトサックスソロ、そして豪快なフィナーレ。
吹奏楽コンクールの全国大会の演奏に「巧い演奏」は当然たくさんありますが、この柏高校の『海の男達の歌』は「心に染みる演奏」。吹奏楽コンクール史上に輝く名演中の名演の一つだと思っています。
プロの演奏としては、海上自衛隊音楽隊のLIVE音源があります。
『海の男達の歌』の音源・CDはどこで手に入る?
amazonと楽天で、土気シビックウインドの演奏CDが手に入ります。『ローマの松』や『青銅の騎士』も収録されていてオススメです!
『海の男達の歌』の楽譜はどこで手に入る?
ブレーンなど各出版社のほか、楽天市場でも購入することができます。
そんなわけで、『海の男達の歌』を紹介しました。そこまで難易度は高くなく、聴き映えのする曲ですので、演奏会にはもってこいです。是非演奏してみてくださいね。
※『海の男達の歌』もランクイン!吹奏楽名曲ランキングベスト10も是非ご覧ください(・∀・)!