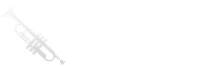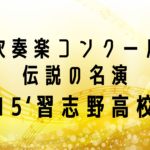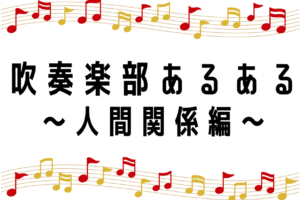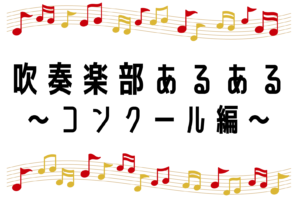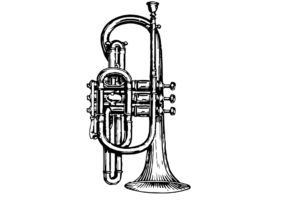本日は全日本吹奏楽コンクールの規定ルールのポイントまとめ。
いわゆる吹奏楽コンクールの全国大会における実施規定です(地区大会や支部大会では微妙に異なる場合もあるのでご注意ください)。
部門ごとの参加人数規定や、審査方法、各賞の割合など、吹奏楽歴が長い方でも、細かい点は以外と知らないかも!?気になる情報をまとめてみます!
全国大会に進む支部はいくつある?
まずは全国大会に進む支部の数について。
これは中学校の部から~職場・一般の部まで共通、全部で11支部あります。
北海道吹奏楽連盟
東北吹奏楽連盟
東関東吹奏楽連盟
西関東吹奏楽連盟
東京都吹奏楽連盟
東海吹奏楽連盟
北陸吹奏楽連盟
関西吹奏楽連盟
中国吹奏楽連盟
四国吹奏楽連盟
九州吹奏楽連盟
複数の都道府県を含まないのが、東京と北海道。沖縄は九州吹奏楽連盟に含まれます。
何県が入っているか少しわかりづらいのが関東ですが、
東関東:千葉・茨城・神奈川・栃木
西関東:埼玉・群馬・山梨・新潟
となっています。新潟は北陸ではなく、なぜか西関東となっています。
各部門ごとに人数制限が違う!?
吹奏楽コンクールに参加できる人数制限。これは実は部門ごとに微妙に人数が異なります。
中学校の部 :50名以内
高等学校の部 :55名以内
大学の部 :55名以内
職場・一般の部:65名以内
微妙に人数が増えていきますね。ちなみにこの人数に指揮者は含みません。
ちなみに参加資格のトリビアをいくつか。
中学校の部では、同一経営の学園内の小学生の参加が、高等学校の部では同じく、同一学園内の小学生、中学生の参加が認められています。
また、大学の部は、同一の大学に在籍していることが条件、となりますので、いわゆるインカレの吹奏楽団は参加できません。
例えば、東京都吹奏楽連盟では、オール早稲田で構成される早稲田大学応援部吹奏楽団が大学の部に、インカレのサークルである早稲田吹奏楽団が、職場・一般の部のコンクールに出場しています。
また、職場・一般の部は、「当該団体の団員」という条件ですので、団体に所属さえしていれば、年齢は問わず、小中学生や高校生の参加も可能です。
また注意しなければいけないのが、同一人物が複数の吹奏楽団でコンクールに出場することはできないということ。これは支部や地区が違ってもNGで、特に職場・一般の部では注意が必要です。
指揮者は職業演奏家OK!?指揮者の規定・ルール
奏者においては「職業演奏家」はNGとされていますが、指揮者の規定については、制限はありませんのでプロでもOKです。
ただし、同一部門で指揮をできるのは1団体まで、となっています。
例えば、高等学校の部と、大学の部でそれぞれ1団体ずつ指揮をするのはOKということですね。
なお、ある意味当然ではありますが、課題曲、自由曲で指揮者を変えることはできません。
余談ですが、今や世界的指揮者でもある佐渡裕さんですが、1986年には龍谷大学を指揮して全国大会初出場に導いています。
演奏の制限時間は!?
吹奏楽コンクールには制限時間があり、12分以内。
課題曲の演奏から、自由曲の演奏終了まで。課題曲の演奏と自由曲の演奏の間の演奏していない時間も含まれるので要注意です。
演奏時間をオーバーすると失格となり、審査対象となりませんので、演奏時間については事前にしっかりと確認、シミュレーションしておきたいところですね。
近年要注意!課題曲における規定・ルール
次に課題曲について。
近年ルールも、その順守のチェックも非常に厳しくなってきており、注意が必要です。
まずスコアに指定された編成で、楽譜通りに演奏しなければなりません。
音をオクターブ上げたり、別の楽器の譜面を吹いたりするのもNGで、近年違反が厳しく取り締まられる傾向にあります。
歌詞アリの歌はNG!自由曲における規定・ルール
次に自由曲です。
編成は、木管楽器、金管楽器、打楽器(擬音楽器を含む)となっています。例外として、コントラバス、チェレスタ、ピアノ、ハープはOKです。
歌声については、スキャット、ハミングはOKですが、歌詞はNGとなっています。
自由曲で注意しなければならないのが、編曲。著作権のある楽曲は、当然ですが、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければなりません。
また、課題曲と自由曲は当然のことながら同一メンバーで演奏する必要があります。ただし楽器の持ち替えはOKです。
金賞は全体の何%?審査・表彰の規定・ルール
次に、審査・表彰の規定です。
審査員の人数は原則として9名となります。
出場団体は、金賞・銀賞・銅賞のいづれかを受賞します。
一般的には、金:銀:銅=3:5:2 等と言われたりすることもありますが、全日本吹奏楽コンクール審査内規を読むと、割合に関する規定はありません。
審査内規をまとめると
審査員は、各部門及び、前半の部・後半の部ごとに、課題曲と自由曲を総合し、A(金)・B(銀)・C(銅)の3段階で評価
↓
理事会で年度毎に定められるA・B・Cの数が、審査説明会で審査員に伝えられる。
↓
審査員は各部門及び前半の部・後半の部ごとに、A・B・Cのの数を厳守して審査
【結果】
① 審査員の過半数がA評価:金賞
② 審査員の過半数がC評価:銅賞
③ ①・②以外 :銀賞
となっており、「各賞の数については制限を設けない」と審査内規に明記されています。
その他規定・ルールのトリビア
最後に、ちょっと気になる、規定・ルールのトリビア。
全国大会に15回出場した指揮者は「長年出場指揮者」として表彰することができるそうです。
佐藤正人さんや、近藤久敦さん、精華女子・活水の藤重佳久先生、習志野高校の石津谷治法先生など、吹奏楽界のレジェンド指揮者が表彰されています。
さて、そんなわけで、「全日本吹奏楽コンクールの規定・ルールのポイント」をご紹介いたしました。吹奏楽コンクール参加の際の参考になれば幸いです(・∀・)!
※本記事は、以下内容を参照しております。改訂されるものは極力追って更新しますが、古い情報が残っている可能性、解釈の間違い等が絶対にないとは言い切れませんのでその点ご容赦くださいませ。また本記事を参照して発生した事象やミス等については免責とさせてくださいませm(_ _)m
・全日本吹奏楽コンクール実施規定 平成27年3月20日更新
・全日本吹奏楽コンクール審査内規 平成27年3月20日更新