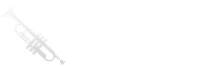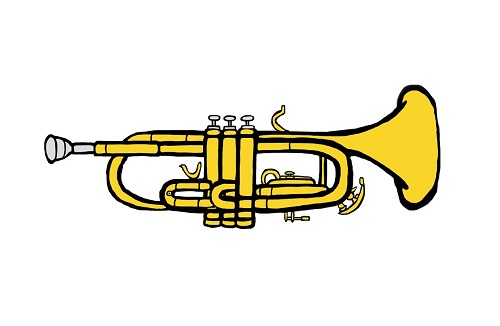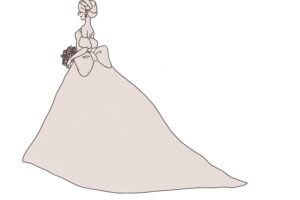吹奏楽の名曲、人気曲、吹奏楽コンクール課題曲編。今回は『吹奏楽の為の序曲』 をご紹介します。
『吹奏楽の為の序曲』はいつの課題曲?
作曲者は坂田雅弘(Masahiro Sakata)、平成12年度(2000年) 第48回 全日本吹奏楽コンクールの課題曲Ⅳです。
この年のその他の課題曲は、
Ⅰ 『道祖神の詩』(福島弘和)
Ⅱ 『をどり唄』(柏崎真一)
Ⅲ 『胎動の時代-吹奏楽のために』(池辺晋一郎)
というライナップ。1年ごとに交互にマーチとマーチ以外の課題曲の時期で、マーチ以外の課題曲の年です。
この年はどの部門でも大きな偏りなく4曲が満遍なく演奏されていたイメージで、名曲揃いの年の印象ですが、中でも『吹奏楽の為の序曲』は吹奏楽民と話していると「自分の学校はやらなかったけど、実はこれが一番やりたかった」という声も多く、人気の1曲です。
ちなみに、1986年第34回大会の課題曲にも『吹奏楽のための序曲』がありますが、こちらは間宮芳生作曲の別の曲。「吹奏楽の為の」ではなく「吹奏楽のための」と平仮名表記になっています。
ちなみにちなみに、、笑
『吹奏楽のための序曲』という名前の曲は、メンデルスゾーン作曲、兼田敏作曲の楽曲もあります。後者は「シンフォニック・バンドのための序曲」と表記されることも多いですね。
『吹奏楽の為の序曲』はどんな曲?
一言で言えば「吹奏楽の魅力の詰まった名課題曲」。金管の華やかさ、木管の美しい響き、打楽器の盛り上げ。そして、疾走感溢れるメロディーと、とゆったりとしたメロディー。
5分間の短い曲ですが、吹奏楽の魅力を余すところなく伝えてくれる名曲です。
冒頭、木管楽器の細かな連符に導かれ、トロンボーンのパワフルなメロディーが登場、トランペットが加わりそれにスネアドラムが合流、疾走感あふれるファンファーレが奏でられます。
6/8拍子の曲で、このメロディーはぱっと聴き変拍子に聴こえる部分がありますが、拍子は6/8拍子のまま。ここカッチリ合わせるのは中々難しく序盤のポイントと言えます。
その後、テンポはそのままに木管の流れるようなメロディーへ。縦の音楽が横の音楽に切り替わります。メロディーはトランペット→木管テュッティと移り変わり、再び冒頭のファンファーレを経て、中間部へ。
中間部は一転、ゆったりとしたテンポへ、木管楽器がロマンティックなメロディーを奏でます。
中間部のポイントはなんといってもトランペットのどソロ。吹奏楽コンクール課題曲には珍しく、長尺のバラードソロです。各学校、各団体が誇るエースが投入されるソロは、この曲の大きな聴きどころです。
テュッティでこのメロディーを繰り返し、クラリネットとホルンのソロリレーで、中間部は終わりを告げ、再び疾走感あふれる冒頭のファンファーレへ。前半部を再度繰り返し、疾走感と勢いを保ったままフィナーレを迎えます。
この曲の終わり方はうまく表現するのが難しいのですが、「次に続く」と言った感じ(笑)
自由曲につながる課題曲として、だけでなく、演奏会で演奏する際にはオープニング曲にピッタリです。
『吹奏楽の為の序曲』の参考演奏~YOUTUBEで聴ける音源~
残念なことに『吹奏楽の為の序曲』の音源はネットにはあまりなく、私が探した限り全国大会の演奏はありません。
通常の参考音源の演奏はありますので、ご参考までに。
『吹奏楽の為の序曲』の音源・CDはどこで手に入る?
amazonと楽天で、東京佼成ウインドオーケストラの参考演奏CDが手に入ります。98年~01年の課題曲が収録されていますが、
98年:『童夢』『稲穂の波』『アルビレオ』
99年:行進曲「K点を越えて」
などなど、課題曲の当たり年が続く年代です。
また、全国大会の演奏もダウンロードで購入することができます。
『吹奏楽の為の序曲』の楽譜はどこで手に入る?
吹奏楽連盟での楽譜の取り扱いが終了し、アレンジ譜も作られていないようです。
どこかの出版社から復刻版が出るのを期待しましょう。
ということで、『吹奏楽の為の序曲』をご紹介しました。演奏会のプログラムで見かけることはあまりないのですが、オープニングにぴったり、奏者も観客も楽しめること間違いなしの一曲です。是非演奏してみてくださいね。
※『吹奏楽の為の序曲』もランクイン!歴代課題曲ランキングベスト10も是非ご覧ください(・∀・)!