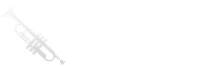吹奏楽の名曲、人気曲、吹奏楽コンクール課題曲編。今回は『稲穂の波』 をご紹介します。
『稲穂の波』はいつの課題曲?
作曲者は福島弘和(Hirokazu Fukushima)、平成10年度(1998年) 第46回 全日本吹奏楽コンクールの課題曲Ⅱです。
この年のその他の課題曲は、
Ⅰ 『童夢』(松尾善雄)
Ⅲ 『アルビレオ』(保科洋)
Ⅳ 『ブラジリアン・ポートレート』(河野土洋)
というライナップ。1年ごとに交互にマーチとマーチ以外の課題曲の時期で、マーチ以外の課題曲の年です。
この年は『童夢』『アルビレオ』も非常に人気があり、課題曲の当たり年と言えます。中でも今回ご紹介する『稲穂の波』は今でも演奏会で耳にする機会もあり、根強い人気を誇っています。
なおこの3曲に人気が分散し、全国大会の高校の部の出場校のうち『ブラジリアン・ポートレート』を演奏した学校が一校もなかったことは当時話題になりました。
なお、作曲者の福島弘和さんといえば、『道祖神の詩』(2000年課題曲Ⅰ)や『梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜』など日本をテーマにした多くの吹奏楽曲で知られています。
『稲穂の波』もその名の通り、日本の秋の田園風景を描写した曲で、綺麗なメロディーが印象的な曲です。
福島弘和さんの魅力は、それこそ、コンクール課題曲のような比較的平易な曲から『ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶』のような難曲まで、吹奏楽の幅広い層に支持される様々な曲を世に送り出しているところでしょう。
『稲穂の波』は福島弘和さんの曲の中でも人気曲で、代表曲とも言える曲ですが、個人的には、歴代課題曲の中でも「屈指の名曲」だと思っています。
『稲穂の波』が課題曲の中でも「屈指の名曲」と言える理由
1点目は吹奏楽コンクール課題曲でありながら、その年だけでなく、その後も演奏会で演奏され、長く吹奏楽民に愛される記憶に残る名曲である点。
2点目は「課題曲」としても理想的であること。この曲は流れるような綺麗なメロディーが注目されがちですが、緊張感のある出だしや、歯切れのよい表現やアタック、強弱、テンポの揺れなど、バンドの実力が試される要素が随所にちりばめられています。
またテンポ感や表現の幅が広いため、団体ごとに演奏は様々。当時コンクール会場で様々な団体の演奏を聴きましたが、バンドの個性が出やすく、たとえ同じ曲が続いても、聴いている方が楽しめる素晴らしい課題曲だなと感じたのを覚えています。
『稲穂の波』はどんな曲?
『稲穂の波』の特徴の一つが、冒頭の始まり方。
サスペンデッドシンバル奏者はホールの静寂の中、バンドの緊張をたった一人で背負います。笑
しかしながらこの冒頭のポイントはサックスのメロディーが終わった後の、金管楽器。曲冒頭、まだまだしっかり音出し出来ていない中で、勢いとパワーではごまかせないフレーズ。
課題曲の前半部分というのは、コンクールという舞台では印象を大きく左右する大事なポイント。当時コンクール会場で聴いていても、ここの部分でバンドの実力がかなり見えてしまうと感じましたが、まさに理想かつ恐怖の課題曲と言えます(笑)
そして、吹奏楽民の記憶に深く刻まれる、クラリネットの美しいメロディーが始まります。『稲穂の波』はクラリネットパートに自信がなければ、挑んではいけないと言っても過言ではないほど、クラリネットパートのサウンドが随所で重要な役割を果たし、曲の出来栄えを左右します。
しかしながら、このクラリネットのメロディー部分。実のところ勝負は裏の伴奏です(笑)
『稲穂の波』で攻略しなければいけないのが「ゆったりとしたテンポの6/8拍子」。メロディーパートは比較的6/8拍子をとりやすいのですが、伴奏パートはそろえるのが大変。タテはもちろん、音の終わりの処理にも細心の注意が必要。
指揮棒を6つに分けてふれば、タテは揃いやすいかもしれませんが、曲調を考えたらご法度。ゆったりとしたテンポの6/8拍子を「2つ振り」でコントロールしきれるか、指揮者の実力も試されます。
冒頭のメロディーはフルート、アルトサックスに受け継がれ、再びクラリネットに戻りますが、クラリネット以外の楽器になった時に、色彩感の変化を出せるか、もポイントです。
その後、木管楽器のテュッティのメロディーを金管打楽器の伴奏が盛り上げた後、曲調が大きく変化します。
ホルンを皮切りにテンポが大きくアップ。強豪と呼ばれるような団体はここのテンポを指定テンポより速く演奏するケースもよく見られました。
ここのポイントはリズムとアーティキュレーションの正確性。動きながらハッキリとしたタンギングをスピード感をもってやらなければいけないリード楽器にとってはハードな部分です。
また木管楽器、金管楽器共に「タッタタ」が連続する付点音符のリズムが肝中の肝。このリズムが詰まったり、間延びしたりすると目立ちますし、曲の流れを止めてしまいます。
その後、拍子が2/4へ変化して曲はさらに盛り上がりをみせ、再び6/8拍子へ。しかしながら、この勢いのまま終わらせてくれないのが「理想の課題曲」たる所以(笑)
再び冒頭の、ゆっくりとしたテーマに戻り、静かに曲が終わります。落ち着いた綺麗なサウンドと、ハーモニーが再び要求されますから、奏者は最後の最後まで気が抜けません(笑)
吹奏楽名門校による『稲穂の波』の名演~YOUTUBEで聴ける音源~
前述の通り、『稲穂の波』は学校によって個性が出て、どの音源も新鮮で聴いていて楽しいです
まずは東関東支部が誇る3強のうち、柏高校と常総学院高校の演奏を紹介します。
柏高校は、subPや強弱の変化、微妙なテンポ揺らしがとても印象的。常総学院は中間部のテンポの速さと力強さが印象的。
これはあくまで個人的な主観ですが「ドラマティック演奏の柏」「正確無比でパワフル演奏の常総学院」という印象をまさ表現している演奏だなと感じます。
次に一般の部の名門、アンサンブルリベルテ。さすがリベルテ。クラリネットパートのクオリティーの高さ半端ないです。
また、通常の参考音源の演奏もあります。
『稲穂の波』の音源・CDはどこで手に入る?
amazonと楽天で、東京佼成ウインドオーケストラの参考演奏CDが手に入ります。98年~01年の課題曲が収録されていますが、
98年:『童夢』『アルビレオ』
99年:行進曲「K点を越えて」
00年: 『吹奏楽の為の序曲』
などなど、課題曲の当たり年が続きますね。
『稲穂の波』の楽譜はどこで手に入る?
オリジナル版は復刻されていませんが、小編成版がブレーンから出ています。
各出版社や楽天でも購入することができます。
ということで、『稲穂の波』をご紹介しました。長く愛される名課題曲、まだ演奏したことのない方は、是非演奏してみてくださいね。
※『稲穂の波』もランクイン!歴代課題曲ランキングベスト10も是非ご覧ください(・∀・)!